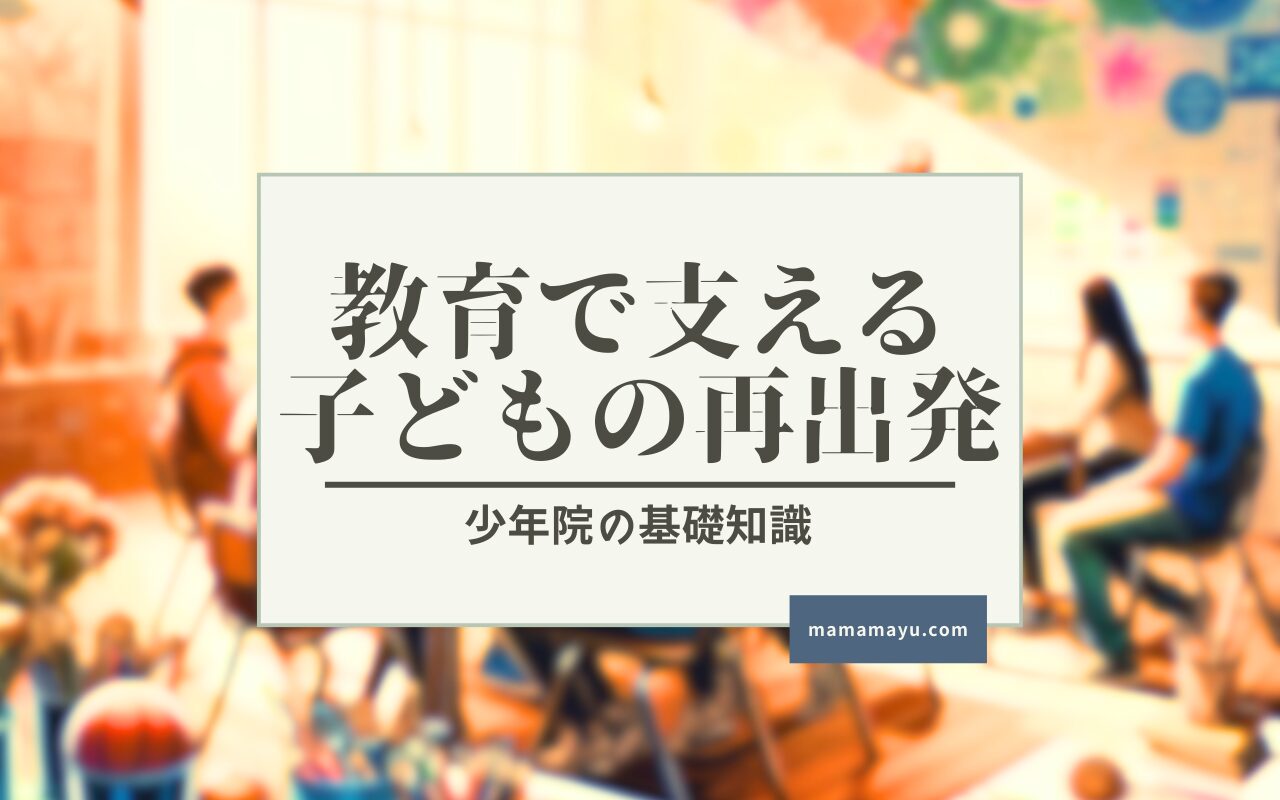「少年院」と聞くと、多くの人が暗いイメージを抱くかもしれません。
特に犯罪被害に遭われた方々やご家族にとっては、非常に複雑な思いを抱く場所だと思います。
過ちを犯した子どもが再び社会に戻れるよう、さまざまな支援を行う少年院。
今回は、初めて少年院のスタディツアーに参加することになった私個人の予習を兼ねて、少年院の仕組みについて書きます。
被害に遭われた方々の傷を決して軽視せず、同時に、更生の可能性を諦めず支援することも社会の重要な役割だと私は感じています。
この記事が、少年院や非行防止に興味を持ってもらったり、教育の多様なあり方と可能性について考えたりするきっかけになれば幸いです。
ちなみに本記事は令和6年版犯罪白書に基づいて書いていますが、法令や制度は随時改正される可能性があります。
最新の正確な情報は、法務省や関係機関の公式サイトでご確認ください。
また、本記事の内容は、犯罪被害に遭われた方々の心情を考慮しつつ、教育的観点から少年院の制度を紹介することを目的としています。
特定の立場や意見を支持・否定する意図はありませんこと、ご理解ください。
少年院の基本的理解
少年院で行われる教育支援の内容に入る前に、まずは少年院の基本的な仕組みと制度について理解していきたいと思います。
「少年」とは
この記事では、「子ども」という言葉の代わりに「少年」という言葉を使います。
少年とは、20歳未満のことを指します。性別は関係ありません。
成人と違い、少年はまだ人格形成の最中で、適切な教育や支援によって更生の可能性が高いとされ、成人と区別した取り扱いが法律で定められています。
「非行」とは
少年による犯罪は、非行と呼ばれます。
少年が反社会的な行為や、法律に違反する行為をしてしまったときに、「非行少年」として扱われます。
非行少年は、更に年齢などの基準でさらに3つに分けられますが、ここでは割愛します。
非行の背景には、家庭環境の問題、学校での不適応、貧困、発達上の課題など、様々な要因が複雑に絡み合っていることがあります。
「非行少年」=「悪い子」とひとくくりに決めつけることはできません。
家庭裁判所の役割
非行少年の処遇は、ほとんどの場合、家庭裁判所で決められます。
令和6年版犯罪白書によると、2023年は41,943人が家庭裁判所に送られたそうです。
これは前年比から18.9%増でしたが、60-80年代のピークと比べると、人口比でみても大幅に減少している数字です。
家庭裁判所は、少年の年齢、非行の内容、家庭環境、更生の可能性などを総合的に考慮し、以下のような処分を選択します。
2023年に多かった順に並べてみました。
- 審判不開始:家庭裁判所が審判を開かずに手続きを終了。非行事実が認められない、または審判に付すことが相当でないと判断された場合。2023年は18,645人。
- 保護観察:社会内で更生を図る処分。保護観察官または保護司による指導を受けながら、通常の生活を送る。原則として20歳に達するまで。2023年は10,081人。
- 不処分:審判の結果、特に処分を必要としないと判断された場合。2023年は8,061人。
- 検察官送致:刑事処分が相当と判断された場合。特に重大な事件や16歳以上の故意の犯罪による死亡事件など。2023年は2,933人。
- 少年院送致:12歳以上の少年について、専門的な矯正教育が必要と判断された場合。2023年は1,623人。
- 児童自立支援施設等送致:18歳未満の者について、比較的軽度の非行の場合。2023年は135人。
- 児童相談所長等送致:主に14歳未満の少年について、児童相談所での処遇が適当と判断された場合。2023年は117人。
こうして並べてみると、少年院への送致(上記5)は、非行を犯した少年に対する処分の一つであり、全体のなかでは少数派の印象です。
この記事は、少年院見学のための事前学習なので、少年院にフォーカスします。
少年院とは
少年院とは、「家庭裁判所が少年院送致の決定をした少年を収容し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育、社会復帰支援等を行う施設」です。(令和6年犯罪白書より)
2024年4月1日時点で、全国に43庁(分院6庁を含む)設置されており、法務省が管轄しています。
少年院入院者の数は、2000年(6,052人)をピークに減少傾向にあり、2023年は1,632人(ただし前年比22.5%増)とのこと。
2023年入院者の1,632人のうち、女子は134人(8.2%)です。
少年院は教育と更生を目的とした施設であるという点が、刑務所とは大きく違います。
矯正教育の5つの柱
少年院では、在院者の年齢や心身の状態、非行の内容などを考慮し、個別の教育計画に基づいた矯正教育と、社会復帰を支援するためのさまざまなプログラムが提供されているそうです。
中心となるのが「矯正教育」。
矯正教育とは、非行少年の健全な育成、改善更生と円滑な社会復帰を実現するための専門的な教育のことです。
生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導の5つの分野で構成されています。
それぞれの分野で専門的な知識やスキルを持つ職員が指導にあたっています。
1. 生活指導
在院者が社会生活を送る上で必要な基本的な生活習慣や態度を身につけるための指導。
具体的には、起床・就寝時間、食事、清掃、身だしなみなど、規則正しい生活を送るための訓練や、問題行動の原因を探り、改善するためのカウンセリングなどが行われるそうです。
また、被害者の視点を取り入れた教育や、薬物非行防止、性非行防止、暴力防止の指導も組み合わせ、他者への思いやりや規範意識を育もうとしています。
さらに、家族関係を見つめ直し、より良い関係を築くための指導や、友人関係における適切な距離感やコミュニケーションスキルを学ぶ機会も提供されています。
2. 職業指導
在院者が将来的に自立した生活を送るために必要な職業に関する知識や技能を習得するための指導。
「職業生活設計指導」では、ビジネスマナーやパソコン操作、キャリアカウンセリングなど、社会人として必要な基礎知識やスキルを学び、
「職業能力開発指導」では、ICT技術、建設技術、農業、木工、手芸など、様々な分野の職業訓練が行われます。
資格取得講座も設けられていて、2023年における出院者のうち、溶接、土木・建築、ICT等の資格・免許を取得した者は延べ1,140人だそうで、さらにフォークリフト運転や危険物取扱者等の資格・免許を取得した者は延べ1,676人だったそう。
自分の興味や適性を見つけ、技能を身に着け、将来のキャリアプランを具体的に描くことができるような制度になっています。
3. 教科指導
少年院には、義務教育未修了者や、中学校・高等学校への復学を目指す在院者のために、小学校、中学校や高等学校の課程に準じた授業が行われています。
実際2023年には、中学校または高等学校への復学が決定した者はそれぞれ15人、51人いて、在院中に中学校の修了証明書を授与された者は63人とのこと。
また、法務省と文部科学省の連携により、少年院内でも高卒認定試験が実施されており、2023年の受験者数は424人、合格者数は162人、一部科目合格者が239人だったそうです。
4. 体育指導
体育指導では、体力づくりや運動能力の向上を目指した指導が行われています。
集団スポーツを通じて、協調性やフェアプレー精神も養われますね。
5. 特別活動指導
さらに特別活動指導では、在院者の情操教育や社会性の育成を目的とした様々な活動や行事が行われています。
自主的活動、クラブ活動、情操的活動、行事及び社会貢献活動などが含まれます。
社会復帰支援
社会復帰支援は、在院者が社会に円滑に復帰するための包括的な支援です。
年齢やニーズに応じて、就労、復学、福祉などの分野の支援が組み合わされます。
就労支援
法務省は、厚生労働省と連携し、就労支援対策を実施しており、少年院、保護観察所、ハローワークが連携して、在院者の就労を支援しています。
2023年の出院者のうち、就労支援の対象者に選定されて支援を受けた者は409人(30.8%)、そのうち就職の内定を得た者は156人(出院者の11.7%、就労支援を受けた者の38.1%)だったそうです。
復学支援
高校や中学等への復学をする在院者に対し、出院後の円滑な復学等を図るための支援もあります。
福祉支援
障害を有し、かつ、適当な帰住先がない在院者に対して、出院後速やかに福祉サービスを受けることができるようにするための調整もあります。
出院後の展望
2023年の少年院の出院者の数は1,328人。
平均在院期間は、短期の対象者で144日、長期の対象者で389日。
出院者の進路は、就職決定が39.2%、進学決定が1.1%、中学復学決定が1.1%、高等学校復学決定が3.8%、短期大学・大学・専修学校復学決定が0.3%、就職希望が36.6%、進学希望が13.9%、進路未定が2.0%だったそうです。
就職決定/希望が相対的に多いですね。
しかし、厳しいデータも存在します。
2023年における再非行少年の数は、5,721人(前年比21.3%増)とのこと。
さらに2019年の少年院出院者2,065人について、5年以内の再入院・刑事施設入所率は21.2%となっています。
2000年から2019年までの各年の少年院出院者の5年以内の再入院・刑事施設入所率はずっと21~24%台を推移していて、この20年あまり変化が見られていないようです。
この数字からは、社会復帰支援の難しさを示すとともに、より効果的な支援策の必要性が見られます。
まとめ
少年院見学の予習として、私が基礎知識として知っておきたかったことをまとめました。
参考にしたのは、法務総合研究所の『令和6年版犯罪白書』です。
少年院は、個々の特性やニーズに合わせた教科教育、職業訓練、生活指導、就職支援など、多角的なアプローチで少年の成長と社会復帰を支援するための施設だと確認しました。
調べてみた率直な意見としては、なんとなく寄宿制学校を連想するほど「教育施設」という側面はかなり強いなという印象です。
(ボーディングスクール出身者にしかわからない「あるある」32選)
あるいは、そもそも私がそういう見方に偏っているのかもしれない。
少年院での矯正教育は重要な役割を果たしていますが、あくまで少年の社会復帰支援のための数ある制度の一つです。
それはいわば「最後の砦」であって、本来であれば、もっと早い段階での予防的支援や介入が望ましいでしょう。
家庭、学校、地域社会、様々な機関や場所が連携して初めて、少年の健全な育成と社会復帰が実現できるのだと思います。
見学の際には今回の学びをさらに深め、現場のリアルな課題や、教育の可能性を肌で感じてきたいと思います。
そして、そこで得た経験を、またこの場で共有したいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
本記事の内容は、犯罪被害に遭われた方々の心情を考慮しつつ、教育的観点から少年院の制度を紹介することを目的としています。
特定の立場や意見を支持・否定する意図はありません。
最新の正確な情報は、法務省や関係機関の公式サイトでご確認ください。